KENSYO>能狂言インタビュー バックナンバー
|
|
KENSYO vol.76
観世流 シテ方 片山 幽雪
YUSETSU KATAYAMA
舞台歴七十年。
能楽界の至宝
「幽雪」の新たなスタート
|
 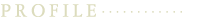
片山 幽雪(かたやま ゆうせつ)
観世流シテ方。昭和5年生まれ。観世華雪、観世雅雪に師事。昭和11年、仕舞『猩々』で初舞台。14年、初シテ『岩船』、以降多くの舞台を勤め、最奥の『姨捨』『鸚鵡小町』『檜垣』『関寺小町』まで披演。京都観世会会長、京都能楽会理事長、能楽協会理事長などの要職を歴任。平成2年日本芸術院賞、6年紫綬褒章、7年芸術院会員。13年重要無形文化財個人指定(人間国宝)に認定。21年度文化功労者。ほか受賞多数。
|
|
雪明かり。
雪の下では、早や花の莟(つぼみ)が芽生え、その色がほのかに灯っている。若い女のかぐわしさ、老いたる女にもにじむように漂う品格の香り。それを、余すところなく表わす美しい名前、幽雪。
この新年から、観世流二十六世宗家より許された「雪」号の文字を用いる雅号である。九世片山九郎右衛門さんは、自ら、幽雪というやさしい響きの名を考えた。
それにつづき「老分(ろうぶん)」を宗家から命じられた。「芸事総監督」という片山家初めての重い役割である。観世流全体の芸事を見守っていくことになる。
また、平成二十一年度の文化功労者として顕彰された。シテ方では、明治以来、三人目である。
「有り難いことです。運が良かったのや、と思います」
という幽雪さんのこれまでの歳月は、けして、平坦な道のりではなかった。
幽雪さんは昭和五年、八世片山九郎右衛門、四世京舞井上八千代の長男として京都に生まれた。観世華雪(かせつ)、観世雅雪(がせつ)に師事。シテ方を継承していくことに迷いなく、一度も悔いることもなかった。自分の稽古だけでなく、師や他の弟子を喰い入るように見て学び、舞台も熱心に見て、能そのものを心身に吸収していった。
少年時代は戦争であった。学徒として建物疎開に出て、皆で建物を網で引き壊す作業は「厭でしたね」。京都にも空襲はあり、片山家の菩提寺に爆弾が落ちた。当時、丸太町通りにあった観世能楽堂は強制疎開で取り壊された。鏡板と舞台板のみ、辛うじて運び出したが、舞台下の信楽焼の瓶(かめ)は戦時の用水桶に使われた。幽雪さんは野菜作りなどで食料難をしのぎ、おかげで好き嫌いはなくなった。
ひろ子さんと結婚。長女の五世井上八千代さん、長男の十世九郎右衛門となる清司さんをもうけた。京女のひろ子さんの、家を守りたてる気概と支えを得て、能と舞の家の長としての役目を果たしてきた。
父君が急逝されたのは昭和三十八年三月十日であった。神戸で『求塚(もとめづか)』を演能中、倒れられた。父君に付き添い京都へ戻り、弔問客の応待をしている間、幽雪さんは、涙もこぼさず、冷静であった。人々が去り、静かになった深夜。お父様に、
「何で、死んだんや」
初めて声を掛けた。三十三歳であった。
二か月後、幽雪さんは、京都観世会館で、『求塚』を舞う。辛かったらやめてはどうか、の周囲の声もあったが、幽雪さんは恬淡(てんたん)と舞った。感傷はなく、父君が倒れた、
わが身、捨てゝん──
の後がやれたな、と思った。その翌年、清司さんが生まれた。父君の生まれ代わりとも思い、いとおしい分だけきびしい稽古をつけた。
また、嘉永年間、五世片山九郎右衛門の小書きに依(よ)る『三輪(みわ) 白式神神楽(はくしきかみかぐら)』の正しい伝承にも力を尽くしてきた。そして、片山家のことのみでなく、観世流ひいては能楽界の発展の努力も惜しまず、京都観世会会長、京都能楽会理事長、能楽協会理事長など勤めてきた。
平成十六年春、三月十九日、お母様がみまかられた。幽雪さん、清司さん一行はニューヨークで公演中であった。公演にさしつかえないよう、ひろ子夫人は清司さんにだけ伝え、八千代さんらと共に、お母様の死を伏せ、静かに待った。その生まれ代わりのように、四日後、清司さんの長男、清愛(きよちか)さんが誕生した。それはニューヨークの幽雪さんに伝えられた。「おめでとう」と清司さんに祝いの言葉を掛けた。数日後、成田空港で、悲報を告げられた。父君の時と同じように、「人はこうして死んでいくのか…」、無常を噛みしめた。
そして舞台に、役職にと多忙な日々がつづき、舞台歴七十数年になろうとする一昨年、足にしびれを覚えた。腰も不調であった。
「隠居するか。現役をつづけるか」
躊躇することなく腰の手術をし、リハビリに励んだ。両足に1㎏ずつの鉛の重りを付け、舞台にのぞむ。毎日、舞台の上を歩く。旅公演に出ても能舞台を借りて、少しでも舞台の上を歩くように心がけている。
「自分の足を、毎日、確かめたいのでね」。
返せや返せ、昔の秋…
『姨捨』の気品あるたたずまい。幽雪さんは、今年の十一月に国立能楽堂で「姨捨」を舞う。ただ立ち、月を眺め月とたわむれているだけの、まさしく幽玄の世界をくりひろげたいという。老いて爪先を上げず太ももで進む歩みも、それ自体が老いを超越した美しい風姿となっていくのである。その歩みがやがて匂いやかな花の風情をはらみ、抑制されたノリのある舞にさしかかると、舞台と見所は、ひとつにつながっていく。
「必死に稽古をすること」
幽雪さんは、若い能楽師たちに教える言葉を、自らの心身でもって伝えているのである。
厳しい稽古の末に極めた地位と栄誉に甘んじることなく、生涯現役であるという気迫に満ちている。
インタビュー・文/ひらの りょうこ 撮影/墫 怜治
●ページTOPへ
●HOME
|
|

