KENSYO>能狂言インタビュー バックナンバー
| |
KENSYO vol.82
金春流 太鼓方 三島元太郎
GENTARO MISHIMA
メロディをはらんだ
太鼓の音色 |
 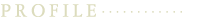
三島 元太郎(みしま げんたろう)
金春流太鼓方。日本能楽会員。
1936年生まれ。故三島太郎の長男。父三島太郎および故前川宗閑、故柿本豊次、金春惣右衛門に師事。2006年旭日双光章を受賞。国立能楽堂(太鼓)研修講師、大阪能楽養成会(太鼓)講師など意欲的な活動をみせる。 |
|
音が飛んでくる。
ひとつひとつの音が円く感じられる。一閃の音のかすかな余韻が色づいていてそれが緒のようになって次の音につながっていく。見所に飛翔して円形の輪のようになって舞台へつながっていく。
金春流太鼓方。三島元太郎さんの太鼓はいつもそんな風に、とてもメロディアスに聴こえて、胸もとにふわりと心地よく響く。太鼓は、能の後半の場面でのシテの舞に演奏され、激しい闘いや怒り、呪いといったものが多い。また、神様や天仙、時に皇帝など高貴な人の登場の折に欠くべからず音楽としてつかわれる。
しかし、三島師の太鼓はそれらの場面のいずれにおいても、メロディをはらんだ色合いがある。その不思議についてぜひ、お聞きしたいと思いつつ、大阪吹田のお宅へうかがった。昔ながらの町家のけいこ場の風情のなかに太鼓が置かれてあって、それはまるで三島師の家族のような存在感があった。
太鼓から何かしらメロディが聴こえてきます、
と問いかけると三島師はちょっといたずらっぽく微笑んだ。
「クラシックが好きです。とくにマウリツィオ・ポリーニのピアノが好きです。どの曲といわれると、やっぱり、ベートーヴエンのピアノ・ソナタですね。そういったことが、私の太鼓の音色に含まれているのかもしれませんね」
横書きに書かれてきた西洋の古典、あるいは縦書きに記され口伝されてきた日本の伝統芸。洋の東西を問わず自然やさまざまないきものから学び、そこから見出し、創ってきた芸術は、今となっては人類の最も尊い伝統なのだろう。
しかしまた、人類がおかした戦争は、その貴重なものの消失にもつながっていく。三島師はその真っ只中に生き、能楽、太鼓の繁栄のために尽くしてきたひとりである。
昭和十一年(一九三六)大阪堀江に金春流太鼓方、三島太郎師の長男として生まれた。姉と妹の三人きょうだいであった。おとなしい子どもだった。六歳の六月六日。前川宗閑師(一八九三|一九七八)に弟子入りする。
また父君にも稽古をしてもらっていた。しかしわが国は太平洋戦争に突入していく。元太郎少年は小学校、当時の国民学校の高学年になり、家族と離れ島根県へ学童疎開に。疎開地でも太鼓のことを思いつづけていた。お国のためにすべて捨てようと唱えた人たちは歌舞音曲をやめよ、といったが、
「多くの人は残さなくてはならない、と考えていたと思います」
現実は生活が成り立たず、戦後、父君は勤めに出てしのぎつつ、父子は稽古を怠らなかった。そんな時、三島師は、橋岡久太郎(観世流シテ方一八八四|一九六三)さんの舞を見て強く胸うたれた。囃子方もすばらしく、三島青年の心は騒ぐ。ぼくも太鼓を打ちたい。そんな折、文部省が能楽の若手の養成を始める、と報道で知る。このままでは囃子方が消えるという危機感もあり、三島師は迷わず上京。高校を卒業した十八歳だった。
東京は駒込の染井能楽堂(現在、横浜能楽堂に復元)を管理していた師匠の元に住み込み、養成会で学び、能楽堂の掃除や管理を手伝い、家事をしながら宗閑師、金春惣右衛門師、柿本豊次師(一八九三|一九八九)の各氏の薫陶を受けた。研修を五年、さらに内弟子としても励む。
「東京は面白いですよ、今も」
すでに大阪での出演もしていて、新幹線のない頃から、東京、大阪また北海道など各地に出向いた。
太鼓は叩くとはいわない。
「叩くというと、何か表面的な感じですね」
打つ。打ち込む。力づくではなく、むしろ肩の力を抜いて、その力は手首に集約される。そして、その形はこれまで、さまざまに工夫されてきた。
金春流の「半月」と呼ばれる撥を持つ左手が半分、胸の前をよぎる構え。これは、そこから太鼓の中心のお月様のような円形が、半分に見えることからいう。
打ち込む深さ、エネルギーは大、中、小とあるが、小さい音にはたくさんのバリエーションがある。左手が陽。右手は陰という。
演奏前に胴に革を張り、締める。
革は常に自然な状態にしておく。天候によって、乾燥、湿気を見極め、いくつかの中から選ぶ。
「敢えていえば、私は細いというか、小さな胴が好みです。胴は太鼓のいのちですからね。引き音というか品、音が大切です。重い、軽いもあります。また背の高い、低いもあります。時代によって好みが変わっていくということもありますね」
三島師は、中学生の頃から締めつづけてきた。
美しい蒔絵の楚々として静かにそこにある。「僕らは職人。何かをやってやろうと思わない方が良い」と語る三島師のように。
ほどいて、最後に台がたたまれると、それもまた、楚々とした人の形をしていた。
インタビュー・文/ひらの りょうこ 撮影/八木 洋一
●ページTOPへ
●HOME
|
|

