KENSYO>能狂言インタビュー バックナンバー
| |
KENSYO vol.86
観世流 シテ方
観世清和
KIYOKAZU KANZE
観阿弥・世阿弥の故郷・奈良で見る
観世宗家の格別の舞台
|
 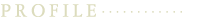
観世 清和(かんぜ きよかず)
二十六世観世宗家。1959年生まれ。父は二十五世宗家・観世左近。1990年に家元を継承し、室町時代の観阿弥、世阿弥父子の流れを汲む二十六世観世宗家として、現代の能楽界を牽引する。国内公演はもとより、フランス、インド、タイ、中国、アメリカ、ドイツ、ポーランド、リトアニアなどの海外公演、及び『箱崎』『丹後物狂』『阿古屋松』などの復曲、『利休』『聖パウロの回心』をはじめとする新作能にも意欲的に取り組んでいる。芸術選奨文部大臣新人賞受賞、フランス文化芸術勲章シュパリエ受章。重要無形文化財「能楽」(総合認定)保持者。社団法人観世会理事長。財団法人観世文庫理事長。一般社団法人日本能楽会常務理事。独立行政法人日本芸術文化振興会評議員。東京芸術大学音楽部講師。著書に『一期初心』などがある。
|
| |
|
夏の日差しが照りつける午後、若草山の麓に建つ奈良県新公会堂で下申し合わせを終えたばかりの観世流宗家が、忙しいスケジュールながらもインタビューに快く応じて下さった。
ここ数年、多方面でのご活躍が目をひきます。
―ご承知のとおり、先代の家元(父 25世観世左近(元正):1930―1990)が満60歳と1ヶ月で急逝したんですね。私も今年で53歳になりましたが、親の歳を超えるというのは親孝行だとかねてより思っておりました。自分のためだけではなく、能楽の世界を一般の多くの方々に情報を発信しつつ、ご理解いただくことが大切ではないかなという思いが強くあります。こういうものは一過性ではなく、常に継続して情報を提供していく必要があると思うのです。もちろん、情報を提供していくだけではなく、私ども日々の稽古を積んで、そしてお客様によい舞台をご披露申し上げることが使命だと思います。世阿弥も伝書の中で「珍しきが花」と言葉を残しておりますけれども、珍しいだけではなく、中核にある真の強さ的なものを現代人にアピールしていかないとならない気がするのです。いまは東京の観世会で年6回、能以外の題材をご専門に研究なさっている先生方をお招きをして能楽講座を開催させていただいております。
門戸を広げるご苦労や工夫もおありかと思いますが。
―底辺拡大というのは大変よいことですが、その手段として私どもがどこまでおこなってよいか、というところが大事だと思うのです。こちらもいろいろ材料を提供して導入部につなげていくことが大事だと思いますが、なんでもやればよいというのではなく、どこまでかみ砕けばよいか、ここがなかなか難しいところです。いいものは残してゆかないといけないと思いますし、現代にマッチしない、ナンセンス的なことはゆっくりした速度で、柔らかく、よい方向に変えてゆくということは必要ではないでしょうか。
宗家が10月に演じる『安宅(あたか)』公演には、「奈良結崎発祥観世流特別公演」というサブタイトルがつけられている。現在シテ方には5つの流儀があるが、観世流のもととなったのは、南北朝時代に大和(奈良県)で活動していた猿楽芸能の一つ・結崎(ゆうざき)座である。結崎座に所属し、大夫(座の代表する役者)をつとめていたのが観阿弥で、観世流の初代にあたる。息子の世阿弥とともに京都へ進出し、将軍足利義満の庇護のもと各地に勢力を伸ばしていくこととなる。それからおよそ700年近くたった現在、その流れをうけつぐ26世宗家が、発祥となる奈良の地で能を舞う。
―世阿弥自身、「大和」という地域に対しては原点回帰と思っていたのですね。能『采女(うねめ)』がそうです。華やかな北山第(だい)で義満の寵愛をうけた立場にあっても、南都六宗だとか大和の地に対しては、常に目を向けていたのです。室町幕府側のいわゆる政治的な色合いを出している彼の作品であっても、望郷の念が色濃く残っているものがたくさんあると思う。大和・奈良に対する思いがあるのではないでしょうか。
尋ねると、宗家がこれまで奈良で能を演じたのは、わずかに数えるほどしかないという。
お父様の七回忌追善能で『安宅』を初演されたそうですね。
―それ以降は数十回勤めさせていただいております。実は先代の父は、晩年まで『安宅』を勤めていなかったのです。それには理由がありまして、喜多流の後藤得三さん(1897―1991)の、あのいぶし銀のような『安宅』をいずれは勤めたい、という思いがあったのですね。痩せていた父に比べて弟の観世元昭(1937―1993)は身体の大きい人で、『安宅』を自分の十八番にしておりました。非常に豪壮華麗な弁慶だったのです。それを若かりし頃から父は観ていたので、俺の目指している『安宅』は違う、弟の真似はできない、と。ずっとやらなかったのですが、50歳前後の頃に『安宅』を初めて勤めました。その日の晩に私に「おい、清和。面白いな〜、『安宅』」って言ったのですよ。非常に印象的でした。
能のなかでも人気が高い『安宅』は、焼失した東大寺大仏殿再建のため、諸国行脚して寄付を集めていた山伏姿に身を替え、あるはずもない勧進帳を読んで、からくも安宅の関を通り抜けようとする義経一行の逃避行を描く物語である。会場となる奈良県新公会堂は、すぐ近くに国宝・東大寺大仏殿がそびえ立つという絶好のロケーション。
お父様はどこに面白さを感じておられたのでしょうか。
―一つの舞台に何十人もいるのに「心理劇」というとらえ方をしていたようです。常に義経や同山(ツレ、義経の郎等)を見渡している…。私は実際に後藤得三さんの『安宅』を拝見したことがないのですが、父にいわせると「古格(こかく)」を守った『安宅』だった。見た目に派手ではないのだけれども、内面の充実感が発露されるみたいな…。
やはり理想はお父様の『安宅』になりますか?
―そうですね。謡でも「先代はこのように謡っていたなぁ」というのが身体の中に入っておりますから。勧進帳はうわべの節付だけで謡ってはだめだ、なぜここでこういう節がついているのかというところまで掘り下げて稽古をしないと成立しないよ、と。弁慶は命をかけて勧進帳を読み上げるわけですから。そのような事が稽古をしているときに断片的にふっと蘇ってくるのです。金剛杖で義経を打つところも、ふわぁっと力が抜けているのですよ。でもお客様には本当に打っているように見えている。やはり演技の迫真性というのでしょうか。主君に対しては、どんな窮地になっても本当に力を込めて打てない弁慶の優しさというか…。強く打ってもいいのですが、そこに父の思いのような、美的感覚があると思います。
宗家から見た『安宅』の魅力は?
―父もそうでしたけれども、常に主君義経を中心として集団行動をしている姿。郎等が関所を通過する際に、弁慶は後ろにも眼があるような、常に気を配っているかのようなものを一貫していないと成立はしない。だから子方の義経も、ツレの同山も、非常に重要な役柄です。それこそシテ一人主義ではできない。みんなの気持ちが一つになりはじめて成立する演目だと思います。
ワキ(富樫)も重要ですね。
―弁慶と義経を富樫は最初からわかっていたかがポイントです。あるおワキの方は「人による」と仰います。弁慶の義経を守ろうとするひたむきな姿を見ていると、何となく「心配しないで、誰にも言わないよ」って。そのような気持ちになっていると言うのですよ(笑)。シテの演技力におもわず引き込まれて、それこそ純粋な感動が湧いてくる。また他のおワキの方は「最初から知っいるのだよ。だから“虎の尾を踏み毒蛇の口を逃れたる心地して”のところは涙が出そうになるのだよ。富樫も気がついたら判官贔屓になってしまった」と言われた。あぁこれも一つの面白い解釈だなぁ、と。義経を金剛杖で打擲するところでも、先ほど申し上げたような(ふわぁっと打つ)動作を見ていて、富樫が「な?言っただろ?義経なんだよ」。それを思わせることが大切な世界なのですよ。
お能は人間そのものをあらわしているのです。たまたま義経と富樫と弁慶という具体的な人間を使っておりますが、本当は人間の本質をお客様に伝え、ご覧頂くということが根幹にあると思います。
家元として伝統を受け継ぐことの大切さ、そして能の魅力をアピールしていく中で、観阿弥・世阿弥の故郷・奈良での公演は格別の舞台となるにちがいない。
インタビュー・文/北見真智子 撮影/八木 洋一
●ページTOPへ
●HOME
|
|

