KENSYO>能狂言インタビュー バックナンバー
|
|
KENSYO vol.98
ワキ方福王流
福王和幸
KAZUYUKI FUKUO
さあ、どうする、この舞台――
|
 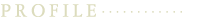
福王 和幸(ふくおう かずゆき)
福王流ワキ方。1973年兵庫県生まれ。
福王流ワキ方十六世宗家福王茂十郎の長男。父に師事。4歳で初舞台、1983年「岩船」で初ワキ。1997年「道成寺」と「張良」、1998年「羅生門」を披く。1995年「大阪咲くやこの花賞」受賞。東京芸術大学卒。
|
| |
 月の名近き秋なれや。月の名近き秋なれや。姨捨山を尋ねん 月の名近き秋なれや。月の名近き秋なれや。姨捨山を尋ねん
姨捨山に捨てられた老女の思いを受け止める都人。秋煌々と照り輝く満月と、山に捨てられた老女がひとつになったように思える時間が訪れ、和幸さんはその一瞬を見届けるひとりの旅人となったー。
六月、大阪の大槻能楽堂で上演された「姨捨」でワキの都人を勤めた。
シテは人間国宝の梅若玄祥さん。玄祥さんにとっても、この時の「姨捨」は、自身の能人生の集大成ともいえる舞台であった。その相手役に、自分より二十五歳も若い和幸さんを抜擢したのだ。
「ところが、橋掛りからおシテの老女が出てきた瞬間、ああ、あのおばあさんで来られたらとても今の僕の技量では受け答えできない、と思いました。頭を回して回して、一行ずつ言い方を変えたりしましたが、これはあかんと」
玄祥さんの老女は「山に捨てられているのに悲しそうでもなかった。それでいて『姨捨』なんです」。そう言って美しい唇を引き結んだ。「まだまだ経験値が必要。試練ですね」
若い時から能楽界、期待のホープとして注目の存在だった。
ワキ方三流のうち、唯一関西に本拠を構える福王流の十六世宗家、福王茂十郎さんの長男として生まれ、幼いころから父の薫陶を受け、父のツレを数え切れないほど勤めてきた。四年前から東京に本拠を移し、多い時は東京と関西を月に十回以上往復しながら舞台を勤めている。
180㎝を超える長身に端正なマスク、気品漂う舞台姿を見るため、あえて脇正面に座る女性ファンが多くいるほどである。
しかし当人は周囲の思惑には脇目もふらず、能の道に精進してきた。
「あまり他のことに興味がないんです」と苦笑する。「歌舞伎も文楽も一回行ったぐらいかな。映画も見ないですし…。ああ、でも、興味があるといえば、野球の阪神タイガースの応援ですね。甲子園が近いので、狂言の善竹隆司さん、隆平さん兄弟と行ったりしますよ」
どこか自分を客観的に見ているようなクールさが魅力。そこが実はワキの本質につながっているのかもしれない。それが筋金入りのタイガースファンとは。ちょっと、驚いた。
父で師の茂十郎さんの稽古の厳しさは有名だった。「比べられるものではないですが、多分、他の方々よりはずっと」と言葉少なに語る。
「あ」と一文字発声すると即、「違う」と言われる。どう違うかは教えてもらえない。必死で考える。何度も繰り返していると、「それ」と言われる。「でもこちらは当てずっぽうでやっているので二回目は出来ない。ただ、自分で考えるお稽古をしていただいたおかげで、いま舞台に立たせていただいている。ありがたいと感謝しています」
福王流の継承者として生まれ、そうなることが運命づけられてきた。しかし幼いころから抵抗はなく、自然に宿命を受け入れたという。「だからといって若い時から能の面白さがわかっていたわけではない」という。「ようやく、七、八年前ぐらいからでしょうか」
きっかけの一つは、父がライフワークにしている、現行曲を観阿弥、世阿弥時代の演出に戻して上演する作業。「当たり前ですが、現代人は現代の能しか知りません。しかし僕らは、能が六百五十年の間に変貌を遂げたこと、初演当時はどういうやり方で上演されていたかを知っていないといけない。父たちがしていることはとてつもなく大変な仕事ですが、それを知っているのと知らないのとでは、能を勤めるときの意識が違ってきます」
一曲の舞台のほとんどで、ワキは最初に橋掛りから登場する。その瞬間、和幸さんは思う。「さあ、どうする、この舞台」と。
「僕の第一声で舞台がつぶれるか、つぶれないかが決まってくることもある」。緊張と畏れが交錯する瞬間だ。
「能は、いまは僕にとってなくてはならないものになりました。後世に残さないといけないと思う自分もいる」。ふっと言葉を探した。「でもなぜそう思うかは聞かないでください。いまの僕ではまだわかりません」
美しいワキ方はまだまだ進化を遂げそうな底知れぬ可能性を秘めている。
インタビュー・文/亀岡 典子 撮影/八木 洋一
●ページTOPへ
●HOME
| |

